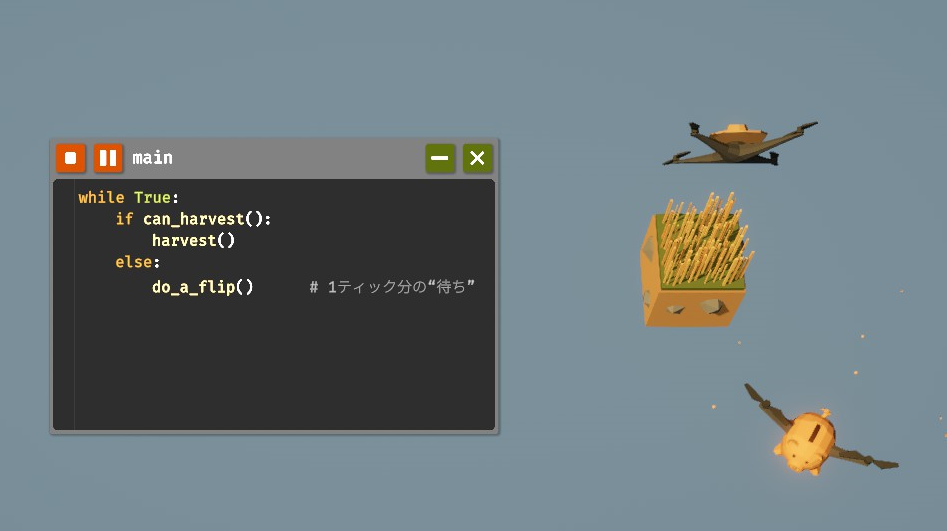当記事はChatGPTが出力した文章を使用しています。
このゲームの関連記事
前回
if文
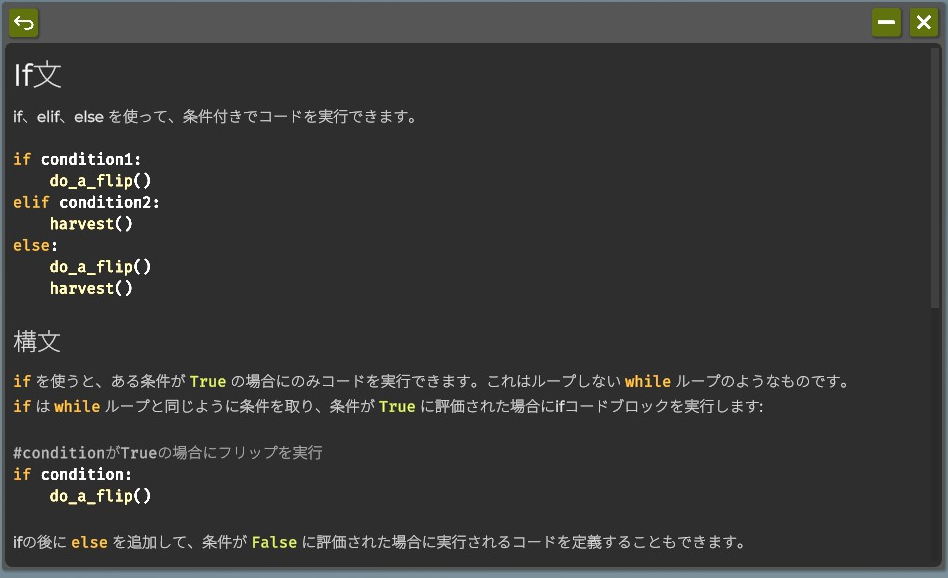
「収穫できる時だけ収穫する」=ムダ打ちしない省エネループ👇
while True:
if can_harvest():
harvest()
-
can_harvest()が True(足元が収穫OK)ならharvest()実行。 -
False(まだ未成熟)なら何もしないで次ループ。
-
ポイント:
can_harvest()の呼び出し自体に1ティックかかるから、同じループ内で2回以上呼ばないのがコツだよ(1回で判定→分岐)。
“速すぎて刈れない” 問題を避ける👀
スピードUPで「成長より手が早い」状態だと、ひたすら空振りになりがち。
少し待ち時間を入れてあげると安定するよ。
見てて楽しい・待ち時間入り版🥳
while True:
if can_harvest():
harvest()
else:
do_a_flip() # 1ティック分の“待ち”
もっと待つ(成長が遅い時)
while True:
if can_harvest():
harvest()
else:
do_a_flip()
do_a_flip() # 2ティック待ってから再チェック
-
考え方:
1回のループで「チェック1ティック+(必要なら)フリップで待つ」を入れて、
成長タイミングに被るチャンスを作る感じね。
if / elif / else の使い分け(今はこう覚えよ)
-
if … 条件を満たしたら実行
-
elif … 別の条件で分岐(今回は他条件がないので無理に使わなくてOK)
-
else … どの条件も当てはまらない時の処理
今の手持ちだと、if + else の2本で十分キレイに書けるよ👌
よくあるミス💣(ここだけチェック)
-
:(コロン)忘れ →if can_harvest():/while True:どっちも最後に必須 -
インデントずれ → TabだけかSpaceだけに統一(混在はエラー)
-
Trueの Tは大文字、can_harvestの 小文字/アンダーバーも厳守 -
if can_harvest:(← かっこ忘れ)じゃダメ。関数は()を付けて呼ぶ!
どれを使えばいい?あいらのおすすめ🌟
-
まずは最小構成(上の一番シンプルなやつ)で挙動確認。
-
「全然刈れない/空振り多いな?」って感じたら、elseでフリップ1〜2回追加してリズム調整。
-
成長→収穫のテンポに合わせて最適な“待ち”を詰める。
コードの実行にかかる時間
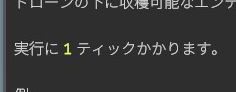
-
このゲームはティック(tick)っていう“カチッ”単位で時間が進むよ。
-
実行時間は「文字数」じゃなくて、実際に実行されたステートメントの数で決まる。
-
1コマンド=だいたい1ティック。だから長いコードでも、動かない行は時間ゼロだし、短いコードでも毎回いっぱい実行されれば時間がかかるって感じ。
いま使えるコマンドのコスト感(超重要)
-
can_harvest()→ 1ティック(説明文に明記されてたやつ) -
harvest()→ 体感 1ティック -
do_a_flip()→ 体感 1ティック -
構文だけの行(
while True:とかif ...:)→ 0ティック -
コメントや空行、インデント → 0ティック
ポイント:分岐やループ自体は時間を食わない。
食うのは中で呼ぶ関数(harvest/flip/can_harvest)だよ。
実行時間はこう数える(例)
例1:ずっと収穫
while True:
harvest()
-
1周あたり 1ティック(
harvest()だけ)
例2:チェックしてから収穫
while True:
if can_harvest():
harvest()
-
収穫できる時 → 2ティック(check1 + harvest1)
-
できない時 → 1ティック(check1 だけ)
例3:待ちを入れる(空振り減らす)
while True:
if can_harvest():
harvest()
else:
do_a_flip()
-
収穫できる時 → 2ティック(check1 + harvest1)
-
できない時 → 2ティック(check1 + flip1)
do_a_flip()を2回にすれば“待ち2ティック”になるよ。else:側の回数でリズム調整するのがコツ💡
「コードが長い=遅い?」への答え
-
文字数や行数そのものでは決まらない。
-
実際に走った関数呼び出しの累計が実行時間。
-
だから、長いけど条件次第で滅多に通らない枝はコストほぼゼロ。
-
短くても毎周
can_harvest()を2回呼ぶ…みたいなのは無駄に遅くなる。
-
スピードアップの影響
-
「速度2倍」は1ティックの“現実時間”が短くなるってこと。
-
でもゲーム内ロジックはティック基準だから、コード設計はティック数で考えるのが正解👌
もし「今の畑で最適な“待ちティック数”が知りたい」ってなったら、else の do_a_flip() の回数を 1 → 2 → 3 と増やしてみて、
-
空振りが多い → 待ちを増やす
-
成熟しても刈り逃す(腐る) → 待ちを減らす
でチューニングしてこ〜🌾🤖✨
ティックは秒数では表せない?
なんで固定じゃないの?
-
スピードUPとかで「1ティックの実時間」が短くなったりする⚡
-
ポーズ/負荷/描画などの影響もあるから、常に○秒=1tickとは言い切れないの。
でも“だいたい”の秒換算はできる?👉できる(自分の環境で計測)
いま解放されてるコマンドだけでできる簡易キャリブレーション💡
方法A:フリップ数から求める(超シンプル)
-
このコードを走らせる(1ループ=1tick)
while True: do_a_flip() -
スマホのストップウォッチで10秒測りながら、フリップ回数を数える。
-
計算:
-
ticks/秒 ≈(フリップ回数)/ 10
-
1tick ≈ 10 /(フリップ回数) 秒
-
例:10秒で 28回 回ったら → 1tick ≈ 10/28 ≈ 0.36秒
※ スピードアップを取ると値が半分くらいになるなど、変化するよ。
方法B:成長サイクルから求める(実務向け)
いま使える if + can_harvest() で「収穫間隔のtick数」を出すやり方👇
while True:
if can_harvest():
harvest()
else:
do_a_flip() # 待ち1tick
-
elseでフリップ1回=1tick待って次チェック。 -
収穫と収穫のあいだに出たフリップ回数を F と数える(目で数えるだけでOK)。
-
その間の総tickは 約 2F + 2(チェック+待ちが2tick/周、最後にチェック+収穫で+2)。
ここで方法Aで出した「1tickの秒」を掛ければ、作物の実時間の育成秒が概算できるよ🌾
まとめ(ギャル要点)
-
1tickの秒は固定じゃない(速度UPや環境で変わる)。
-
でも自分の畑で計るなら、
-
A:
do_a_flip()連打で tick/秒を測る -
B:
if can_harvest()ループで 成長tickを数える
-
-
秒換算=(tick数)×(1tickの秒) でOK💪